50代に入ると、「疲れが取れにくい」「お酒が翌日に残る」「肌の調子が悪い」など、体の不調を感じやすくなる方が増えます。その背景には、加齢に伴う代謝機能の低下や、肝臓の働きの変化が大きく関係しています。
人は40代後半から徐々に基礎代謝が落ち、内臓の機能も少しずつ衰えていきます。特に肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れにくいため、知らないうちに負担が蓄積していることも。
■ 肝臓の重要な役割とは?
肝臓は、次のような生命維持に欠かせない働きを担っています。
- アルコールや薬、老廃物の分解
- 栄養素の代謝(糖質・脂質・たんぱく質)
- 胆汁の生成(脂肪の消化に必要)
- 免疫機能のサポート
つまり、肝臓が元気でいること=全身の健康を守るカギなのです。
しかし50代以降は、これらの機能が衰えがちで、さらに日常的な飲酒が肝臓に大きな負担をかけている可能性もあります。だからこそ今、肝臓を“休ませる日”=休肝日が必要なのです。
実際にどれくらい休めば効果があるの?
「休肝日が大切」とはよく聞きますが、どのくらいの頻度で休めばいいのか?という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。ここでは、医療機関や公的機関の推奨をもとに、休肝日の目安とその理由をご紹介します。
(習慣飲酒者(週3回以上飲酒し、日本酒1合相当以上を飲む者)の割合)
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20代 | 31% | 4% |
| 30代 | 55% | 8% |
| 40代 | 60% | 9% |
| 50代 | 61% | 10% |
| 60代 | 55% | 7% |
50代では男女ともに飲酒習慣が特に顕著で、生活習慣病リスクを高める量の飲酒や頻繁な飲酒が見られる傾向があります。他の年代と比較しても、50代は男女ともに飲酒率が高いことが特徴です。
週2日の休肝日が理想的
厚生労働省や日本肝臓学会などでは、週に2日はお酒を飲まない日を設けることが推奨されています。これは、肝臓の回復に必要な時間を確保し、アルコールの蓄積ダメージを抑えるためです。
ただし、連続して2日設けるのがより効果的とも言われています。例えば、火曜と水曜など、連休のようにまとめることで、肝臓にとってしっかりした「休暇」になります。
週1日だけでも意味がある
週2日が理想とはいえ、いきなり完全に習慣化するのが難しい場合は、まずは週1日の休肝日からでもOK。
実際に週1日の休肝日を継続することで、肝数値の改善や睡眠の質向上を感じる人も多くいます。
“連続飲酒”がもっとも危険
毎日お酒を飲む「連続飲酒」は、肝臓へのダメージが蓄積されやすく、脂肪肝や肝炎のリスクが高まります。
また、知らないうちに「アルコール依存」に近づいてしまう可能性もあるため、1日でも休む日を意識的に作ることが重要です。
飲み過ぎた翌日は“強制休肝日”に
「昨夜はちょっと飲みすぎたな…」という翌日は、体が疲れていたり、胃腸が重いと感じることが多いはず。
そういった日は、意識的に休肝日とすることで、体内のリセット効果が期待できます。
飲酒は“ゼロ”にしなくてもOK。
でも、“毎日”を続けるのではなく、肝臓に休むチャンスを与えることが、50代以降の健康寿命をのばす秘訣です。
50代でも無理なく休肝日を作るコツ
「休肝日が大事なのはわかるけど、習慣になっているお酒をやめるのは難しい…」と感じている方も多いはず。
ここでは、「無理なく続けられる“休肝日の作り方」をご紹介します。
1.「飲まない日」を最初から決めておく
一番のコツは、あらかじめ休肝日をカレンダーに組み込んでおくことです。
たとえば「火曜と木曜は飲まない」と決めておくだけで、「今日は飲んでもOK」「明日は休肝日」と意識でき、習慣化しやすくなります。
私の場合、子供の塾の送り迎えが週に2回あるので、その日を強制的に休肝日にしています。塾に迎えに行って帰ってくると、22時を越えるのでさっさと諦めて、早めに寝ることにしています。
2. 代替ドリンクを用意する
手持ち無沙汰を感じてしまう人には、ノンアルコール飲料や炭酸水、ハーブティーなどの「代替ドリンク」がおすすめ。
特に最近は、本格的な味わいのノンアルビールやカクテル風ドリンクも豊富で、飲みごたえも十分です。
とはいえ、ビール好きの私は、ノンアルコールビールを飲むぐらいならお茶でいい派なので、休肝日は、強炭酸にレモンを混ぜてしのいでいます。
3. 晩酌=リラックスタイムの再定義
「お酒=くつろぎ時間」と思いがちですが、他のリラックス方法に置き換えることも可能です。
たとえば、
- お風呂でじっくり入浴
- 好きな音楽や読書を楽しむ
- 軽いストレッチやアロマを取り入れる
こうした方法でも、一日の疲れを癒やすことができます。
風呂上がりのビールは、格別にうまいんですけどね。私の場合、ブログを書くことや動画編集をすることが楽しいので、晩酌を趣味の時間に置き換えるようにしています。
4. 食事内容を工夫する
お酒の引き金になるのが“味の濃いおつまみ”や“脂っこい料理”です。
休肝日には、野菜中心のさっぱりした和食や、食物繊維・たんぱく質が豊富なメニューを意識すると、飲みたい気持ちを自然と抑えられます。
私の場合、鶏胸肉やささみ、ゆで卵、ブロッコリーなどを入れたサラダボールを食べる日を設けています。自分自身にとって、どの食材が自分にとって有効的なのかわかっていないのですが、確かに夕食のメニューによっては飲みたい気持ちを抑えることができます。
5. 無理に我慢しすぎない
「どうしても今日は飲みたい…」そんな日は、無理に我慢せず、週の中で別の日を休肝日に変更する柔軟さも大切です。
完璧を目指すのではなく、“ゆるく続ける”ことが成功のコツです。
無理なく、少しずつ。
それが、50代からの休肝日を“長く続けられる習慣”にするためのポイントです。
私的には、健康のためと我慢ばかりし過ぎて、死ぬ間際に、「もっとお酒飲みたかった」と後悔したくはないので、ほどほどがちょうど良いのではと思っています。
よくある質問と不安へのアドバイスQ&A
休肝日を始めようと思っても、ちょっとした不安や疑問があると続けにくいもの。ここでは、50代の方からよくある質問にお答えします。
Q1. 休肝日と断酒はどう違うの?
A:休肝日は“お酒と上手に付き合うための方法”です。
断酒は完全にお酒を断つこと。一方、休肝日は「お酒をやめる」のではなく、「肝臓を休ませるために飲まない日を作る」ことが目的です。
飲酒を楽しみながら健康を守りたい方にぴったりの習慣です。
Q2. 飲み会や外食がある日はどうしたらいい?
A:無理をせず、休肝日を別日に調整しましょう。
大切なのは、1週間単位でバランスを取ること。飲み会の予定がある週は、他の日で調整してOKです。完璧主義にならず、「ゆるく継続」することが成功の秘訣です。
私の場合、飲み会がある週は、家でお酒は飲まないと決めています。
Q3. お酒をやめるとストレスがたまらない?
A:最初は違和感があっても、慣れてくると逆に快適になります。
最初のうちは「物足りなさ」を感じる方もいますが、代替ドリンクや新しい習慣を取り入れることで、ストレスなく続けられます。
実際に「体が軽くなった」「寝起きがスッキリした」と感じる方も多く、モチベーションにもつながります。私自身も飲まなかった次の日の朝は、寝起きがスッキリした感じがします。
Q4. 週に1日でも効果はあるの?
A:もちろんあります!
週1日でも肝臓は回復を始めます。大切なのは継続すること。まずは週1日から始めて、慣れてきたら週2日に増やすなど、自分のペースで進めましょう。
Q5. 家族にお酒をすすめられたら?
A:「今日は休肝日なんだ」と堂々と言いましょう。
家族や友人にはあらかじめ「健康のために休肝日を作っている」と伝えておくと、理解を得やすくなります。
周囲の協力も、続けるための大きな支えになります。
最近はお酒自体飲まない人が増えてきたので、昭和的なノリで無理矢理飲まされたりすることもなくなってきました。
休肝日はあなたの健康を守る“やさしい習慣です。無理せず、少しずつ生活に取り入れていきましょう。
50代から始める「休肝日」というやさしい健康習慣
50代は、体調や代謝の変化を強く感じ始める年代。とくに、目に見えないところで働き続けている肝臓は、年齢とともにダメージが蓄積しやすくなります。
そんな今だからこそ始めたいのが、「週に数日の休肝日」。無理な禁酒ではなく、肝臓に休むチャンスを与えるだけで、体と心に驚くほどの変化が訪れます。
- 睡眠の質が上がる
- 肝機能の改善
- 内臓脂肪や中性脂肪の予防
- 気分が前向きになる
- 肌や血圧にもよい影響
…と、嬉しい効果がたくさん。
休肝日は、厳しいルールではありません。
「今週は1日だけ」「飲みすぎた翌日は休もう」など、自分に合ったペースで取り入れることが、長続きの秘訣です。
また、ノンアルドリンクを楽しんだり、リラックス習慣を見直すことで、休肝日はストレス解消にもつながる“自分時間”に変えることができます。
50代からの健康習慣として、今日からぜひ「休肝日」を意識してみませんか?
小さな一歩が、未来の大きな安心につながります。

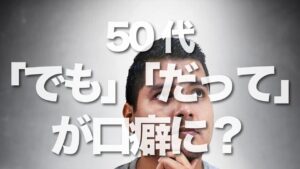







コメント